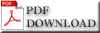第90回 猫の小腸バイオプシーサンプルにおける炎症とリンパ腫の鑑別診断アルゴリズム
猫の小腸バイオプシーサンプルにおける炎症とリンパ腫の鑑別診断アルゴリズム
Vet Pathol 2011
下記のアルゴリズムは画面上では乱れますので、PDFでダウンロード後にご確認ください。
猫の腸管リンパ腫と炎症性腸疾患(以下IBDとする)を鑑別することは臨床医にとっても病理医にとっても診断上の課題である。
この二つの疾患は種類、性別に関わらず中年〜高齢の猫においてよく診断され、最も一般的な臨床徴候は嘔吐、下痢、体重減少、食欲の変動である。
身体検査やエコー、内視鏡検査などだけではIBDとリンパ腫を鑑別するのは困難だが、疾病の転帰や治療が異なるため、正確な診断をすることが重要となってくる。
猫のリンパ腫とIBDの鑑別は通常腸バイオプシー標本の組織形態学的評価に基づいている。
しかし組織形態だけでこの2つの疾患を区別することは非常に難しい場合がある。B細胞性リンパ腫では特徴的な細胞形態を示すのに対し、T細胞性リンパ腫とIBDではHE標本による組織形態学的評価だけでは鑑別できない小リンパ球の浸潤が特徴的となるためである。
猫の腸管リンパ腫(初発)はT細胞起源が多く、IBDでもT細胞性リンパ腫でも粘膜関連リンパ組織(MALT)からT細胞が動員される。
さらにリンパ腫とIBDはしばしば混在する。しかしIBDとは対照的に腫瘍性T細胞は大抵の場合正常な組織を破壊し、粘膜をこえて粘膜下層、筋層、漿膜へと浸潤していく。
ただしルーチンで行われる腸バイオプシーの多くは内視鏡で採材されるため、組織形態学的評価が粘膜に限られてしまう。また、粘膜をこえないリンパ腫である場合も組織評価に病理医間でばらつきが出てくる場合がある。
そのため過去に行われた研究ではリンパ腫とIBDの鑑別は内視鏡検査だけでは不十分であり、十二指腸と回腸の全層標本が推奨されるとも結論づけられている。
IBDと診断されたものの治療に反応せずその後リンパ腫と診断された例もあり、組織学的変化があいまいなリンパ腫とIBDを鑑別するのに免疫組織化学的評価も重要な診断ツールとなっている。
単一なリンパ球の増殖はリンパ腫を示唆し、リンパ球や形質細胞の増殖は炎症を示唆する。さらに上皮内へ浸潤するリンパ球の増加はリンパ腫という診断を支持する要素となる。
またPCRの活用も炎症とリンパ腫の鑑別に有用である。
本研究では63例の猫の小腸バイオプシーサンプルがHE標本による組織形態学的評価、免疫組織化学的評価、PCRによって診断された。
HE染色の組織形態学的評価のみで37例がT細胞性リンパ腫、7例がB細胞性リンパ腫、19例がIBDと診断された。
免疫組織化学的所見とあわせると40例がT細胞性リンパ腫、8例がB細胞性リンパ腫、15例がIBDと診断された。もともと組織形態学的評価のみでIBDと診断された19例中5例はT細胞性リンパ腫として再分類された。
さらにPCRの結果をあわせたところ、43例がT細胞性リンパ腫、8例がB細胞性リンパ腫、12例がIBDと診断された。
まとめると、組織形態学的評価単独でIBDと診断された19例中10例がT細胞性リンパ腫と再分類され、T細胞性リンパ腫と診断された37例中3例がIBDと再分類されたことになる。
そのため、まずHE標本による組織形態学的評価、次に免疫組織化学的評価、最後にPCRでT細胞ないしB細胞のクローナリティ検査をするという段階的な方法をとることで炎症とリンパ腫を正しく鑑別し、適切な治療をすることができると結論付けられる。
【鑑別診断アルゴリズム】
HE標本による組織形態学的評価→→ 炎症 →→→→→→→治療
↓ ↓ ↑ ↓ ↓
リンパ腫 リンパ腫疑い ↑ 治療に反応しない 治療に反応する
↓ ↓ ↓ 免疫組織化学 ← ← ← ↑ ← ←
↓ ↑
T細胞、B細胞の決定 →→→→→→→↑
↓ ↓
リンパ腫 リンパ腫疑い →→ PCRによるクローナリティ検査
↓ ↓ ↓
治療 ←←←←←←←←←←←←←← リンパ腫 炎症(→治療に反応)
パソラボ
記事をPDFでダウンロード