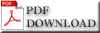第211回 核分裂像・核分裂指数のお話 その1
第211回 核分裂像・核分裂指数のお話 その1
今回も他では語られていない情報を中心に、核分裂像・核分裂指数のお話をしようと思います。核分裂指数が高いのに核分裂像が比較的少ないとは?核分裂像が多いのにどうして良性なのか?など、様々な疑問があるかと思います。総論的な事も含めて、2回に分けて説明いたします。
【核分裂像とホルマリン固定の関係】
腫瘍細胞は分裂を起こしながら増殖していきます。そして核分裂中の細胞はそのままの状態でホルマリン固定され、顕微鏡で核分裂中の細胞として認識されます。内視鏡やコア生検のような小さな組織ではあまり問題にならないと思いますが、大きな組織では固定されるまでの間に時間がかかります。状況にもよりますが、ホルマリンの浸透速度はおおよそ1時間あたり1mmです。
【核分裂像の数は腫瘍摘出後の影響を受ける】
組織辺縁部に存在する腫瘍細胞であれば核分裂中の状態のまま速やかに固定されますが、深部の細胞はそうはいきません。腫瘍が摘出され血液供給が得られなくなった腫瘍細胞は惰性で核分裂を終えることはできても、新たな核分裂を起こすだけの勢いはなくなります。そのため大きさのある組織ではホルマリン固定されるまでの間に、核分裂中の細胞が減っていくという事が起こります。
【バイオプシーよりも摘出組織の方が核分裂指数が低くなる?】
一つの腫瘍の中には核分裂像の多い領域や少ない領域が混在している可能性があります。そのためコア生検において核分裂像の最も多い領域 (一般的に核分裂指数をカウントするところ) が採取される可能性は低いと考えられます。腫瘍が大きければ大きいほどその可能性が低くなります。従いまして本来であれば摘出した腫瘍の核分裂指数はコア生検の際のものよりも高くなるはずです。しかしながら実際にコア生検で検査後に腫瘍が摘出された場合、前者の方が核分裂像が多くなると言ったことは珍しくありません。これはおそらく上記のような摘出後にホルマリン固定されるまでに核分裂を終えてしまうからというのが理由であるのかもしれません。
【核分裂指数による予後は固定など加味されていない統計的数字】
そうであれば摘出した腫瘍組織にいくつもの割を入れて速やかに固定してしまおうという考え方になるかもしれません。しかしながら核分裂指数などによる予後の報告は、沢山の割を入れた組織で統計をとったものではありません。そのためむしろ統計データとは遠のく方向に進んでしまう可能さえあります。また割を入れるということは偽膜が破壊されマージン評価をし難くしたり、腫瘍の全体像を分かり難くしたりと言ったデメリットもありますので、必ずしも固定優先で物事を考えるのは最善とは言えません。
その2に続く
パソラボ
記事をPDFでダウンロード