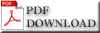第177回 好酸球胃腸炎に関しまして
好酸球胃腸炎に関しまして
リンパ球や形質細胞とは異なり、好酸球は正常では胃腸粘膜にほとんど存在しません。そのためその浸潤が認められる場合には、好酸球性腸炎が考慮されることになります。その数が明らかに多い、粘膜の傷害と再生像が見られる、水腫を伴っている、腸壁が肥厚している、全身状態が悪い、低タンパク血症を起こしているなどといったことがあれば、ある程度診断精度は高くなると考えられます。ただし他の疾患を示唆する所見が存在しないということを同時に確認しておくことも重要になります。これはリンパ球形質細胞性腸炎やリンパ管拡張症においても少数の浸潤が見られることがあるからです。また、ヘルニアなどの疾患で腸管が切除された場合において、偶発的に粘膜に好酸球浸潤が見られるということも時に経験します。つまりは腸炎としての消化器症状を示すことなく好酸球が浸潤していたということになります。このことは腸炎の症状を示してバイオプシーされ、好酸球性腸炎と診断された症例の中にも、好酸球性腸炎ではない症例が混ざっている可能性があることを示唆しています。考え方を変えれば、これはこれで好酸球性腸炎の診断でもよいのかもしれませんが、腸炎の症状を示す症例の中には「好酸球浸潤を伴う好酸球性腸炎以外の疾患」の症例がいることを考慮しておく必要があります。好酸球性腸炎にも疾患の程度や性質にかなりのバリエーションがあるということです。腸炎の診断にはやはり臨床状況や治療に対する反応などを併せて考えていく必要があります。
パソラボ
記事をPDFでダウンロード